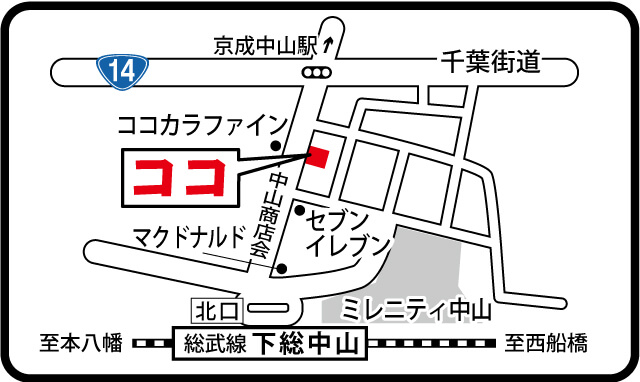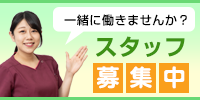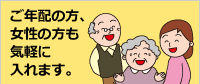こんなお悩みはありませんか?

スポーツ後、膝の痛みでジャンプや走ることができない
階膝を曲げたり歩いたりする際に痛みを感じる
オスグットの症状が続き、日常生活にも支障が出ている
痛みがなかなか軽減せず、運動を再開できるか不安
どの施術方法が最適か分からず、効果が感じられない
膝の痛みが再発するのではないかという不安が常にある
オスグッドについて知っておくべきこと

オスグット病は、膝蓋靭帯が脛骨(すねの骨)の成長軟骨部分を引っ張ることで炎症が生じ、膝の下部に痛みや腫れが現れる疾患です。成長期の子供や若者に多く見られ、特にジャンプやランニングなど膝に負担がかかるスポーツを行う方に発症しやすいです。
オスグット病は、成長が終わる頃(大体16歳から18歳の間)には症状が軽減することが多いです。骨の成長が完了し、膝にかかる負荷が減少することで、痛みが収まることが一般的です。
オスグット病は、通常、成長期に限られた問題であり、大人になると症状がなくなることがほとんどです。
症状の現れ方は?

・膝蓋靭帯が脛骨(すねの骨)の成長軟骨部分に引っ張られ、膝の下部に痛みを感じます。この痛みは特に運動中や運動後に強くなることがあります。
初期段階では軽い痛みを感じることもありますが、症状が進行すると痛みが強くなり、日常生活に支障をきたすこともあります。
・膝の下の腫れ
痛みを伴う部位(膝の下、脛骨粗面)に腫れが見られることがあります。炎症が起きているため、膝周りが腫れたり、触ると温かく感じることもあります。
・膝の下部、特に脛骨粗面(膝の下の骨の突起部分)を押すと痛みが強くなることがあります。圧痛は、痛みのある部位を押したり、膝を使う動作を行ったりすると感じやすくなります。
・膝を曲げたり、膝に負担をかける動作(例えばジャンプや走る)を行うと、痛みが強くなることがあります。これにより、運動時や日常的な動きで制限を感じることがあります。
・特にジャンプやランニングなど膝に負担をかける運動後に、痛みが悪化することが一般的です。運動の頻度が高いと、症状が長引くことがあります。
・長時間膝に負担をかける動作をした後や、スポーツで過剰に膝を使った後に痛みが強くなることがあります。
・炎症が進行すると、膝周りに硬直感や違和感を感じることがあります。膝の動きがスムーズでなくなる場合もあります。
その他の原因は?

成長期の子どもは、骨と筋肉・靭帯の成長速度に差があるため、膝の周囲の筋肉や靭帯が骨に対して過度に引っ張られることがあります。特に、大腿四頭筋(太もも前面の筋肉)が膝蓋靭帯を通じて脛骨(すねの骨)を強く引っ張ることが要因となります。骨の成長が進む一方で、筋肉や靭帯の成長が追いつかないことが、膝に過度なストレスをかける要因となります。
バスケットボールやサッカー、陸上競技など、膝を頻繁に曲げ伸ばしするスポーツに多く見られます。これらのスポーツでは、ジャンプや急な方向転換、ダッシュなどにより膝への負荷が大きくなるため、膝蓋靭帯が脛骨を引っ張り、成長軟骨に負担がかかることでオスグッド病が発症しやすくなります。
特に、急激にトレーニング量が増えた場合や、膝に負担がかかる運動を継続して行った場合には、発症のリスクが高くなります。成長期の子どもは体が発達の途中であるため、膝への負担が蓄積しやすい傾向があります。
また、太ももの前側の大腿四頭筋や膝周りの筋肉が硬くなると、膝にかかる負担がさらに増大します。柔軟性が不足していると膝の可動域が制限され、膝蓋靭帯がより強く引っ張られることにより、膝の下部に痛みが生じる場合があります。
オスグッドを放置するとどうなる?

オスグッド病による膝の痛みや腫れといった症状は、適切な施術や対応を行わずにそのままにしておくと、悪化する可能性があります。症状が進行すると、膝を曲げる動作や歩行といった日常生活にも支障をきたし、運動がさらに制限されることが考えられます。
また、膝に負担をかけ続けた場合、痛みが慢性化してしまい、回復までに時間がかかることもあります。痛みや腫れがあるにもかかわらず運動を続けてしまうと、膝への負担が増し、回復が遅れてしまう可能性がございます。特にスポーツに取り組んでいる方にとっては、無理な運動がパフォーマンスの低下だけでなく、長期間の運動制限につながることもあるため、注意が必要です。
完全に回復するまでに時間を要する場合もあり、その間は思うように運動ができなくなることもございます。さらに長期間放置した場合、膝の成長軟骨に過度な圧力がかかることで、骨の変形や関節のトラブルが発生するリスクもあります。
成長軟骨は膝を支える重要な部位のひとつであり、長期間にわたって炎症やストレスが加わると、損傷が生じる可能性も考えられます。その結果、将来的に膝関節の変形や関節炎などの不調につながることもあるため、早めの対応が大切です。
当院の施術方法について

筋膜ストレッチ
オスグッド病の方には、大腿四頭筋(太もも前面の筋肉)やハムストリング(太もも裏の筋肉)へのストレッチが非常に重要です。ストレッチによって柔軟性が向上することで、膝周囲の筋肉がやわらかくなり、膝への負担の軽減が期待されます。
EMS療法
膝周囲の筋肉を強化することは、膝への負担を分散し、症状の予防や軽減につなげるうえで大切です。特に大腿四頭筋を強化することで、膝への負担の軽減が期待されます。
EMSという電気刺激を用いた機器を活用することで、大腿四頭筋や膝まわりの筋肉の筋力向上をサポートすることが可能です。
改善していく上でのポイント

オスグッド病の症状がある場合は、膝をしっかり休めることが非常に重要です。過度な運動や膝に負担がかかる動作(ジャンプやランニングなど)を避け、安静に過ごすことで炎症や痛みの軽減が期待されます。
痛みが落ち着いた後に運動を再開する際は、無理をせず、徐々に膝へ負担をかけていくことが大切です。急激に運動量を増やしてしまうと、再発の原因となる可能性があるため、段階的に体を慣らしていく必要があります。
膝の痛みが強いときや腫れが見られる場合は、アイシングが有効とされています。冷却を行うことで血流が抑えられ、炎症の軽減が期待されます。アイシングは1回15〜20分程度を目安に、1日に数回行うと良いとされています。
膝周囲の筋肉、特に大腿四頭筋(太もも前部の筋肉)の柔軟性を高めることも重要です。ストレッチを行うことで、膝への負担が軽減され、回復がサポートされます。
また、膝を支える筋肉を強化することで、膝にかかる負担の分散が期待できます。特に大腿四頭筋の強化は、膝の安定性を保つうえで重要とされています。筋力トレーニングは、症状の予防にもつながります。
膝まわりだけでなく、股関節やふくらはぎの筋肉もあわせて鍛えることで、膝全体のバランスが整い、膝への負荷を軽減することにつながります。
運動や歩行時に膝へ余計な負担がかからないようにするためには、足に合った適切な靴を履くことも大切です。特にスポーツを行う際には、機能性の高い靴を選ぶよう心がけましょう。
また、クッション性のあるインソールを使用することで、膝にかかる衝撃の軽減が期待されます。足元から膝への負担を抑える対策として有効です。
膝のサポーターを活用することで、膝の安定性を高め、過度な動きを制限することができます。特に運動を再開するタイミングや、痛みが落ち着いてきた時期にサポーターを使用することで、症状の再発予防や安心して動ける状態のサポートが可能になります。